生成AIへの懐疑的な言説
生成AIの活用が広がるなかで「自分も何か使えるかもしれない」と感じつつ、なかなか一歩が踏み出せないという声を耳にします。
「誤情報は大丈夫なのか」
「本当に信用できるのか」
そうした慎重な姿勢は理解できますし、懐疑的な目線を持つこと自体はとても大切です。中には「すごそうだけど、なんかうさんくさい」と感じている方もいるかもしれません。情報の波に飲まれずに見極めたい・・・そんな気持ちが結果として“使わないまま”になっているのではないでしょうか。それは非常に大きな機会損失です。
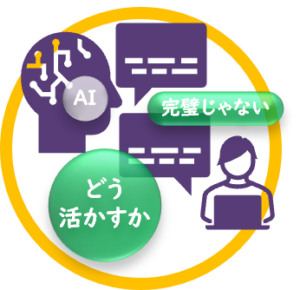
AIは完璧じゃない、でも本当にそれが問題なのか
たしかに、AIは「幻覚(hallucination)」と呼ばれる誤情報を出すことがあります。自身ありげに間違える姿勢に不安を覚える方もいるかもしれません。実際、AIの語り口は非常に滑らかで断定的かつ反応も早いため、内容を吟味する前に“思考を外注してしまう”状態を引き起こしやすいという指摘もあります。
また、AIとの信頼関係に関する研究では、「最初に誤りを示したAIは、後から正確な応答をしても、信頼を回復しにくい」という結果も報告されています。つまり、単に「間違えるから怖い」という話ではなく、語り方そのものが判断力に与える影響に注意が必要だということです。とはいえ、AIの誤りの理由を遠ざけてしまうのは少しもったいないと感じます。
そもそも生成AI云々以前から、私たちの周りに嘘や誤情報はなかったでしょうか。噂やテレビ、インターネットで得たどんな情報であっても、それが真実なのか、どう扱うべき情報なのかは自分自身で判断・確認する必要があったはずです。ここでAIだけに完璧を求めるのは過剰信仰の裏返しではないかと考えます。
たとえば、ChatGPTとMicrosoft Copilot、Geminiなどに全く同じ質問をしてみても、返ってくる答えの粒度や視点が異なることに気づくはずです。これは、それぞれのAIに“得意・不得意”や“くせ”があるからです。人と接する時と同時に「このAIはどう付き合えばうまくいくか」を探る感覚が必要なのです。
「どう使うか」はあなた次第
重要なのは、AIを「正確無比な道具」として扱うのではなく、自分との相性や目的に合わせて活用していくという姿勢です。完璧さを求めるのではなく、どう活かすかを考えることでAIはぐっと身近な存在になります。
私がサポートするクライアントの社内調査では、AI導入による業務効率化や投資対効果の向上が実際に報告されています。とはいえ、「まずは何から使えばいいのか分からない」と感じている方もまだ多いようです。そんなときは、業務ではなく雑談や遊びのような使い方から始めてみるのはおすすめです。たとえば、ひとつの質問を異なるAIに投げてみる。その違いを感じるだけでもAIとの距離が少し縮まるはずです。
技術の価値は「完璧さ」ではなく「活かし方」によって決まります。その点ではAIも人間も変わりません。自分が「使うことができる」力を持つのか・・・いま試されているのは、実はAIではなく私たち自身ではないでしょうか。
2025年7月
